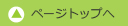大輪作りの基礎知識と技術
vol.1 菊にまつわる話

春の桜、秋の菊は日本人には年齢を問わず、いつどこにいても忘れることのできない日本を代表する花ではないでしょうか。菊の季節がおとずれ、菊の花を日本の誇り、モラルのシンボルのように眺めるのも日本に生を受けたからではないかと思います。
秋も深まりゆくころ、色とりどりの菊が咲き乱れ、その香りが一面に漂い、あちらこちらで菊花展が開催される時、誰しもが「自分も菊を作ってみよう」と衝動に駆られますが、気軽に作ろうとしないのは、菊作りの技術の難しさを誇張される方がいらっしゃるからではないかと思います。
菊作りは、難しいものではありません。菊は、菊自身生育し、美しい花を咲かせようと努力してくれます。理屈を抜きにして、皆さん作ってみたらいかがでしょう。作ってみると菊がいろいろ教えてくれますよ。菊作り教室でお待ちしております。
vol.2 土(培養土)作りから始めよう『培養土作りは菊作りにおいて全ての出発点』

植物栽培で一番基礎をなすものは培養土作りです。特に、菊作りや草花の栽培では、根の張る空間が限られます。大輪3本仕立盆養では、限られた鉢の中で6ヶ月余りの間に健全な茎、葉そして優秀なる花を咲かせる基礎となる大切な培養土です。
培養土の良否がその年の菊作りを左右します。菊作りにおいて、最も多い失敗に腐葉土や培養土の発酵不足があり、更には培養土の通気性不良があります。
このような培養土を使用すると根がいたみ、根ぐされの原因になります。菊作りにおいて手抜きや失敗がゆるされないのが培養土作りです。土(培養土)の力で育てるのが大切であります。
昔から菊は一手かければ一の花が咲き、千手かければ千の花が咲くとよくいわれますが、この忙しい時に千手なんぞかけられない、そこでついつい手抜きを考える。五百手、百手いやもっと節約して50手ぐらいで千の花は咲かないものかと怠け者の寝言、不精者の高望み悪夢の始まりであります。有名な人の栽培法を見るまでもなく手抜きが駄目なことがわかる訳であります。
『千の花を咲かせたければ、千手かけるべし』これが菊作りの秘訣であり、コツなのです。
皆さんも、菊をいつまでも愛し、手抜きをしないで精一杯の大輪を咲かせてください。
vol.3 土つくりは菊づくりの近道!! 腐葉土づくり

菊づくりにおいて腐葉土は有機資源として欠かせない材料の一つであります。
使用する落葉は、葉肉の厚い広葉樹(カシ、マテバシイ等)が理想的ですが、他の広葉樹(クヌギ、ナラ、クリ等)でも問題ありません。腐葉土の未発酵や発酵不足の腐葉土は生育不良(根ぐされ)等の重大な原因になります。落葉を発酵させ腐葉土を作る目的はタンニン等の有害物質を分解除去する大きな目的があります。
腐葉土作りの最も重要な点は、好気性微生物による好気発酵です。落葉を効率よく発酵させ短期日で良質の腐葉土を作るかは微生物の増殖や働きが活発になる条件を備える。この条件を満たす一番大事な点は、空気と水のバランスです。
空気不足(酸素不足)の状態で、発酵が進むと好気性微生物は活動することができなく、空気が嫌いな嫌気性微生物が増殖し、腐敗します。嫌気発酵(腐敗)した腐葉土は卵の腐ったような臭いがするので直ぐわかります。出来上がった物は一見同じように見えますが、そこに繁殖している微生物は全く別物です。病原菌として働くものが多く立枯れなど多発し、植物栽培に適した土にはなりません。
落葉の積込作業を進めるに当り気をつけたい点は、落葉を積み込んだ下の部分に水分がたまり酸素不足で腐敗する場合がありますので気をつけましょう。空気の流通のないもの(ポリ容器等)で落葉を積み込まないこと。
腐葉土づくりで大切なこと
- 好気性微生物による好気発酵
- 有機リン酸の補給
- 米ヌカの添加は多過ぎないこと
良い腐葉土の判定基準
- 暗褐色になっている
- わずかに「カビ臭い」特有の匂いがする
- 手でにぎると形が崩れる
- 発熱があった
vol.4 培養土作りのここがポイント!! 培養土は通気性、排水性が大事!
良い培養土つくりのポイント
 菊作りの良い培養土とは、限られた鉢の中で、根が活発に働き、旺盛な生育をする土です。そのような土とは、通気性、排水性が良く、しかも保水力がよく、根に酸素が十分に供給できることが重要です。そして、有益微生物が良く繁殖し、燐酸分が土に充分に吸収され、効き目がよく熟成された土です。
菊作りの良い培養土とは、限られた鉢の中で、根が活発に働き、旺盛な生育をする土です。そのような土とは、通気性、排水性が良く、しかも保水力がよく、根に酸素が十分に供給できることが重要です。そして、有益微生物が良く繁殖し、燐酸分が土に充分に吸収され、効き目がよく熟成された土です。
材料及び配合割合
- 腐葉土 40%
- 籾殻燻炭 12%
- キクライト(大) 6.5%
- ぼら土(小) 6.5%
- 土(水路の土) 25%
- 浄水場の土 10%
- 米ヌカ=培養土 1,400Lに対し 50L
- 骨粉=培養土 1,400Lに対し 10kg
挿芽
挿芽は菊作りにおいて楽しい時期で、しかも易しいようで難しいのが挿芽ではないかと思います。茎や根を老化させずに、健全な茎、葉を作り、雄大な大菊を作るのも挿芽にあると思います。
挿芽の要領
発根の行われる現象は、オーキシン(ホルモン)の作用によるものです。まず、葉でオーキシンの先駆物質であるプレホルモンが形成され、それが生長部でオーキシンとなって下降して発根します。こういう理論から挿穂の葉の枚数は多くあることが望ましい。
- 挿芽用土は湿らかす前に押しつけておいて、挿芽前日に湿らす。
- 挿芽用土の厚さは3~4cmで、挿穂の切り口は箱の底につける(底挿)。
- 挿穂は天気の良い日に取り、穂先(根元)1cmぐらいを歯ブラシ等でこすり、鹿沼土のダンゴをつけ、更に発根剤をつけて挿す。
- 挿し終わったら、薄いカンレイシャ等で覆いをして、直射日光をさける。
- 潅水は挿芽床が乾燥したとき(5~7日)にやる程度で、その外は朝夕の葉面撒布で葉を湿らかす程度が、発根が早い。